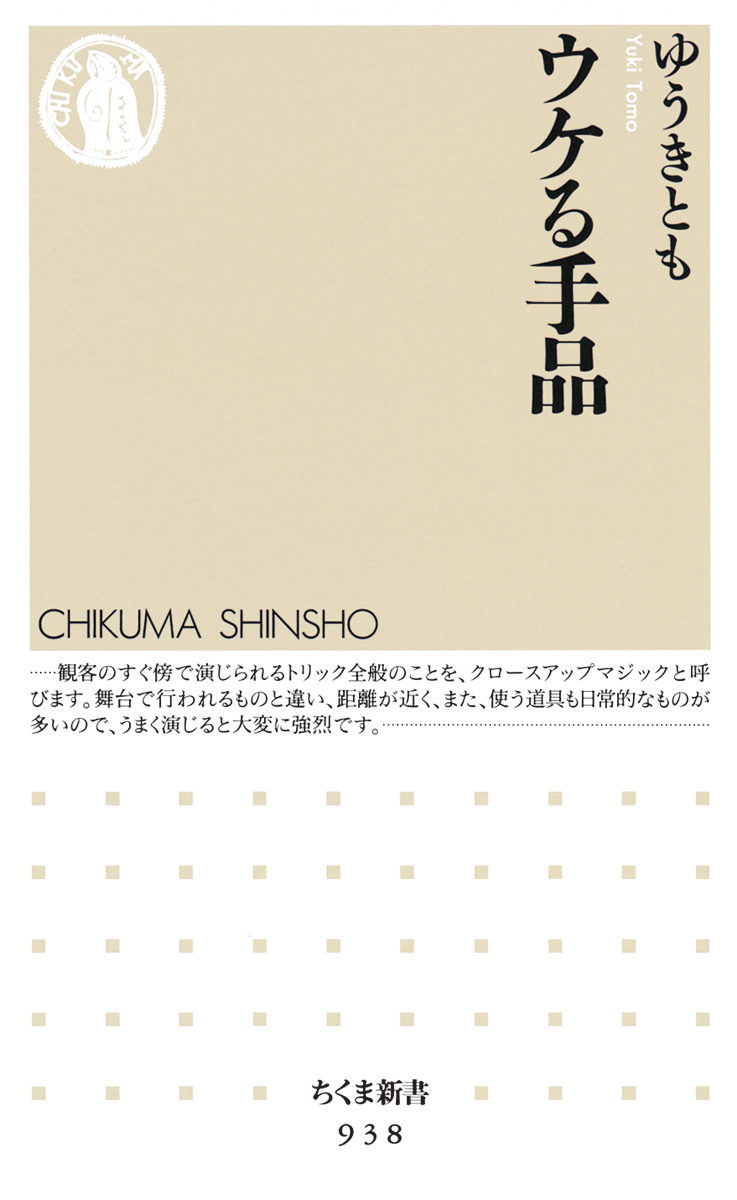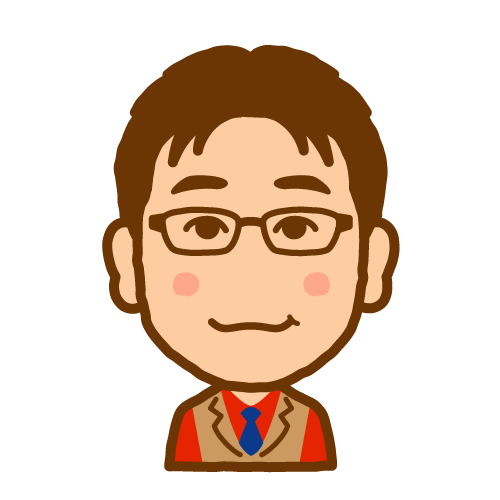筑摩新書。 タイトルは、本来ならばせめて『ウケる為の手品』としたかったところ。一般向けの前提で書いてはおりますが、経験値の高い実践派の方なら、思わずにやりとするお得な情報も満載です。
★福岡在住のプロマジシャンDr.ZUMA氏が鋭い(カッコイイ!^m^)書評をアップしてくれていました。「Dr.ZUMAのお知らせ」2012年2月3日「本の紹介」をご覧ください。
ちなみにアマゾンのレビューにおいて、「ハズレでした」というものがあり、これはまあその方の感想なので、仕方がないことなのですが… この方、おそらくは新しい(自分の知らない)トリックを求めていただけなのかなと感じました。
このページで紹介しているどの本におきましても、まえがきやあとがき、もしくはコラムなどを読んでもらえば、十分にご理解いただけるかと思うのですが、私は決して新トリックの発表を目的としている訳ではなく、マジックの面白さや、マジックとうまく付き合うための実践的なアドバイスを中心に考えて構成しております。
(一般商業書なので、様々な制約はありますがね!)
実際のところ、私はトリックを自分でも考えますし、演じる立場でもありますので、よ~くお読みいただければ、一見よくありがちな古典トリックのようでも、見せ方やセリフなどに様々な工夫を読みとっていただけるはずなのですが…。
★それでは以下に北海道在住の奇術家、綾部祥巳さんからいただいた御感想を紹介します。かなり詳細に内容にも触れておりますので、本をお持ちの方には参考にしていただけると思います。
「ウケる手品」じっくり読ませていただきました。
今回も内容の大変濃い本で、読みながら感心してうなる箇所がいくつもありました。
私が最も感心したのは、各トリックの後に添えられた「演じる際のコツと注意点」の部分です。
これまで出版された解説書で、トリックの演じ方(手順説明)のみならず、その背景となる「考え方」の部分まで言及しているものは、残念ながらそう多くは存在しません。しかしこの本の場合、まさにその点に大きなウエイトが占められており、非常に面白く読ませていただきました。
「演じる際のコツと注意点」 という言い方でまとめられていますが、実際はこの部分は演じる際の「理論」にあたると思います。何に気を配り、何をすべきでないか、またそれはなぜなのか…。そういった、演じる上で意識しておくべき事がよく読むと散りばめられており、大変勉強になりました。
例えば「シンプルイズベスト」「観客への負担軽減」「演技後の観客へのフォロー」「観客に疑いを起こさせないために」「演技の方向性の明確化」「短いフレーズの重要性」などといった、マジックを演じるときに応用できる様々な「理論」がさりげなく書かれています。
紹介しているトリックの数こそ多くはないですが、こういった部分の厚さ、深さこそがこの本の大きな価値であると思います。
また、各トリックの解説の仕方も大変細かく、説明が行き届いていると感じました。
トリック自体の骨格説明だけでなく、せりふやタイミング、具体的な示し方などについても細やかに解説されています。細かいニュアンスの部分というのは、「センス」や「タッチ」といった言い方で演者に任されてしまっている所であり、パフォーマーごとに最も差の出る所でもあります。
演技初心者にとっては(もちろんベテランにとっても)最もむずかしい箇所の一つであるわけですが、「ウケる手品」ではその点の配慮が大変良くなされており、読者が実際に演じるためにどうしたら良いかをしっかり考えて書かれていると感じました。
なにより、日常の中でマジックをどう生かすか、普段の人間関係の中でどのようにマジックを使うのか(これが本当に難しいのです)という観点からトリックが注意深く選ばれているのが素晴らしいと思います。
演者がスーパーマンになりすぎることなく、「ちょっとした話題提供」することで楽しい時間を共に過ごすこと。カジュアルな普段の生活の中で、真の意味でマジックをコミュニケーションに生かすこと。そういうことの難しさと重要性を良くご存知のゆうきさんならではの、こだわりのセレクトとお見受けしました。このセレクト面も、この本の大変ユニークなところだと思います。
長くなってしまいましたので、特に印象に残った二、三のトリックについて述べておきます。
「コイン・シデンス」ですが、相手に左手を握らせる工夫がすばらしいと思いました。これにより三つのアウトそれぞれに等しくインパクトを持たせる意味づけができるのがすごいです。
「お菓子な予言」、パテオフォースの違和感を、チョコを食べるという行為で軽減させてしまうというアイディア、これも思わず唸ってしまいました。
「あなたの負け」、原型はP・ケーンの「バリアント」でしょうか。
実は私は「バリアント」には説得力をあまり感じず、やる気が起きなかったのですが、このやり方ならば大変シンプルで見違えるような面白い作品だと思いました。
これからさらに時間をかけて、書かれているトリックに挑戦したいと思います。そうしながら「行間に」隠れているアドバイスなどを発見できるのを楽しみにしています。素晴らしい本をありがとうございました。(勝手な事を長々と書いてしまいました。どうもすみません…)
綾部祥巳
※ステキな御感想、感謝です。 (^^♪
ちなみに「あなたの負け」の原案は、P・ケーンの「バリアント」です。
原案で使用する技法の代わりに、もう一つのアウトを利用する考えは、マーク・スペルマンのDVDで、丸めたお札の内側に書いておくというアイデアを見たのが最初です。
日本で演じるならば「ウケる手品」で解説した方法が無難でしょう。
このトリックは、一時期自分のショーの中でもよく演じていたのですが、たまたまあるマニアの会で演じたところ、かなり不思議に見えたらしく、あとで高名な研究家の方から問い合わせの電話があって驚きました。 ^^;
ちなみにmMLの70号でも解説しております。
★もうひとつの御感想は、最近ではネットショップ「フレンチドロップ」でのコラムで有名なマジック研究家、石田隆信さんからのものです。読んでいただくと分かりますが、ほぼすべてのネタについて言及してくれております。本当に真面目でマメな方です。 m(__)m
前回の『たのしいマジック』(偕成社)と同様、すばらしい内容で感激しました。今回も失礼かと思いましたが、感激したことを報告させて頂きます。
各作品の最初に、数コマのマンガで現象が紹介されています。これだけで現象が分かるシンプルさが好きです。
しかも、不思議でウケるマジックばかりなので嬉しくなります。
知っている原理でも、興味を引く演出が加わっていて、使ってみたくなります。
また、ウケるための見せ方や注意点が、大いに参考になります。
最初の名刺を使ったマジックは、マニアには衝撃的だと思います。こんなにシンプルにして大丈夫かと不安に感じます。少し考えられると、種の原理がばれる恐れがあるからです。もちろん、十分すぎるほどの不思議さがあります。この不安に対して、これまでの経験と考え方を紹介されていたのが印象的です。
さらに、二つの別法も解説されていて、嬉しくなります。
カードではなく、名刺を使った演出にしているのも、ウケる要因だと思います。
コラムの中で触れられていました「基本的にはマジシャンにならない方が得」や、「ハードルは常に下げておいた方が得」は新鮮に感じました。一般の人がマジックを演じやすくするためには、取り入れるべき考え方と思いました。
2番目の名刺のマジックもすばらしいのですが、演技後のことも考えられていたのには脱帽しました。
コラム「クロースアップマジックの本当の難しさ」でも、その点に触れられていて参考になります。
3番目のコイントリックは、シンプルでエキボック使用の理想型といえます。
演じ方に注意して、正しく行わないと、ウケ方に大きな差が出ることがよく分かります。
4番目の名刺でのオルラム・サトルティを使用したマジックもかなり不思議です。そこに記載された注意点は重要だと実感しました。
これら以外の作品でも、マーブルチョコを使った素材の楽しさ。ケータイの着信音を効果的に使ったニクイ演出。客が運が悪かった人にならないための一言の配慮にも感心させられました。
ダイレクトで不思議さが強烈であったのは、バラや三角形の予言マジックです。これらには、保険としてのパテオフォースがあり、安心して演じることが出来ます。オープンにして演じるマジックと、秘密の部分を隠したまま行うマジックとの違いを、はっきりさせているのも画期的です。オープンにして演じる「はずれる乾電池」や「天国と地獄」や「指から抜けるストラップ」は、私も好きな作品です。
オセロやダイスのマジックは、面白い原理と種です。テクニカルな二つのコインマジックもシンプルで効果的です。一般の人には少し難しく感じますが、頑張れば出来るマジックです。
そして、収録された18作品の中で、私がレパートリーとして以前からよく演じていたのが「リンクト」です。1977年発行のハリー・ロレイン著「ザ・マジックブック」を読んでから、取り入れるようになりました。面白い発想で不思議ですが、不思議さが十分に伝わりにくいようです。よく注目させていないと、いつの間にかつながっているので、ごまかされた印象があるのかもしれません。その点の改善のために、強調すべきポイントを考えましたが、そのことは全て書かれていましたので、さすがと思いました。
長々と感想を書いてしまいました。これまでの本とは、一味違ったすばらしさがありました。これからもご活躍を楽しみにしております。